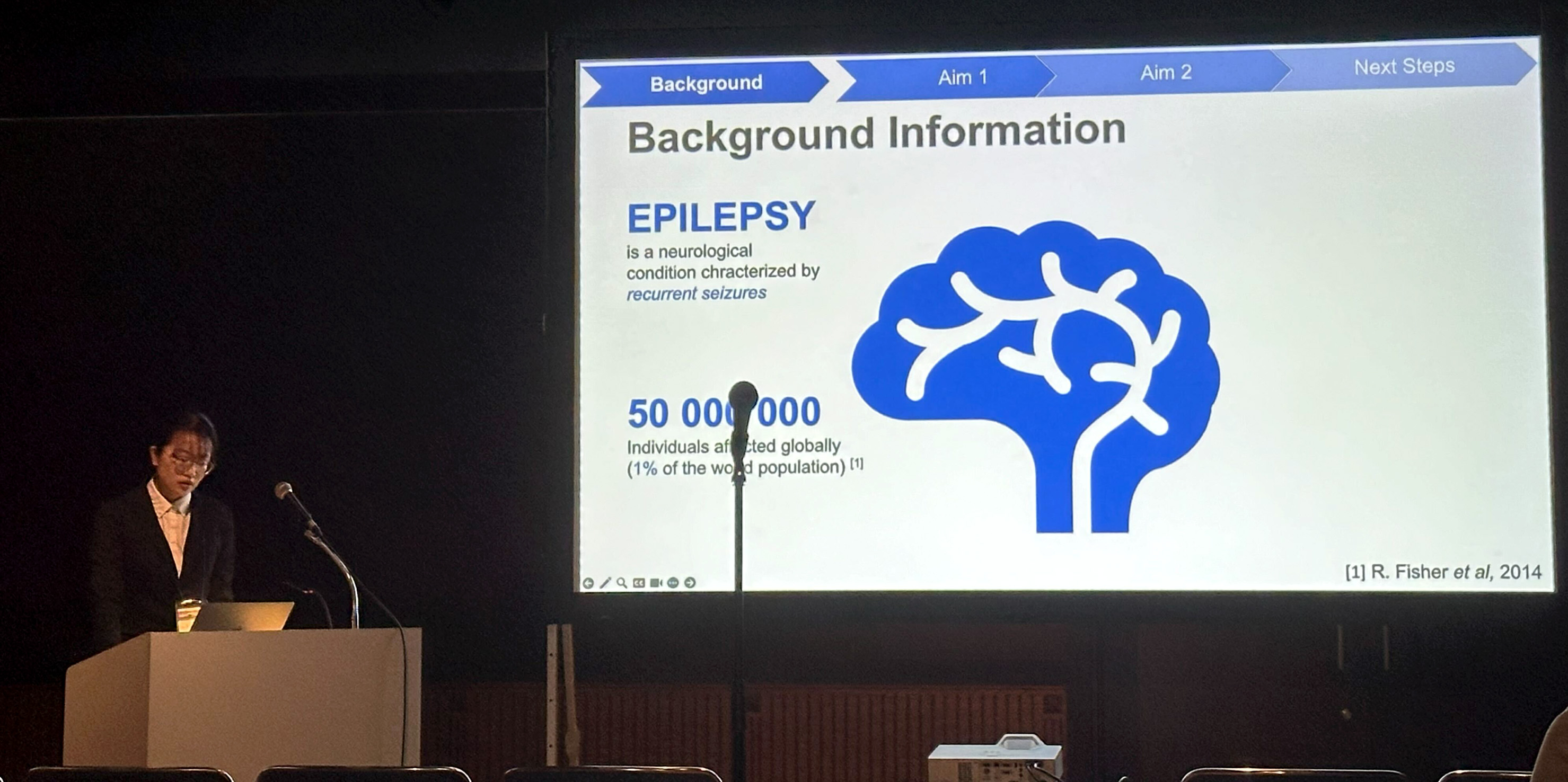
日本で研究発表
フルブライトストーリー
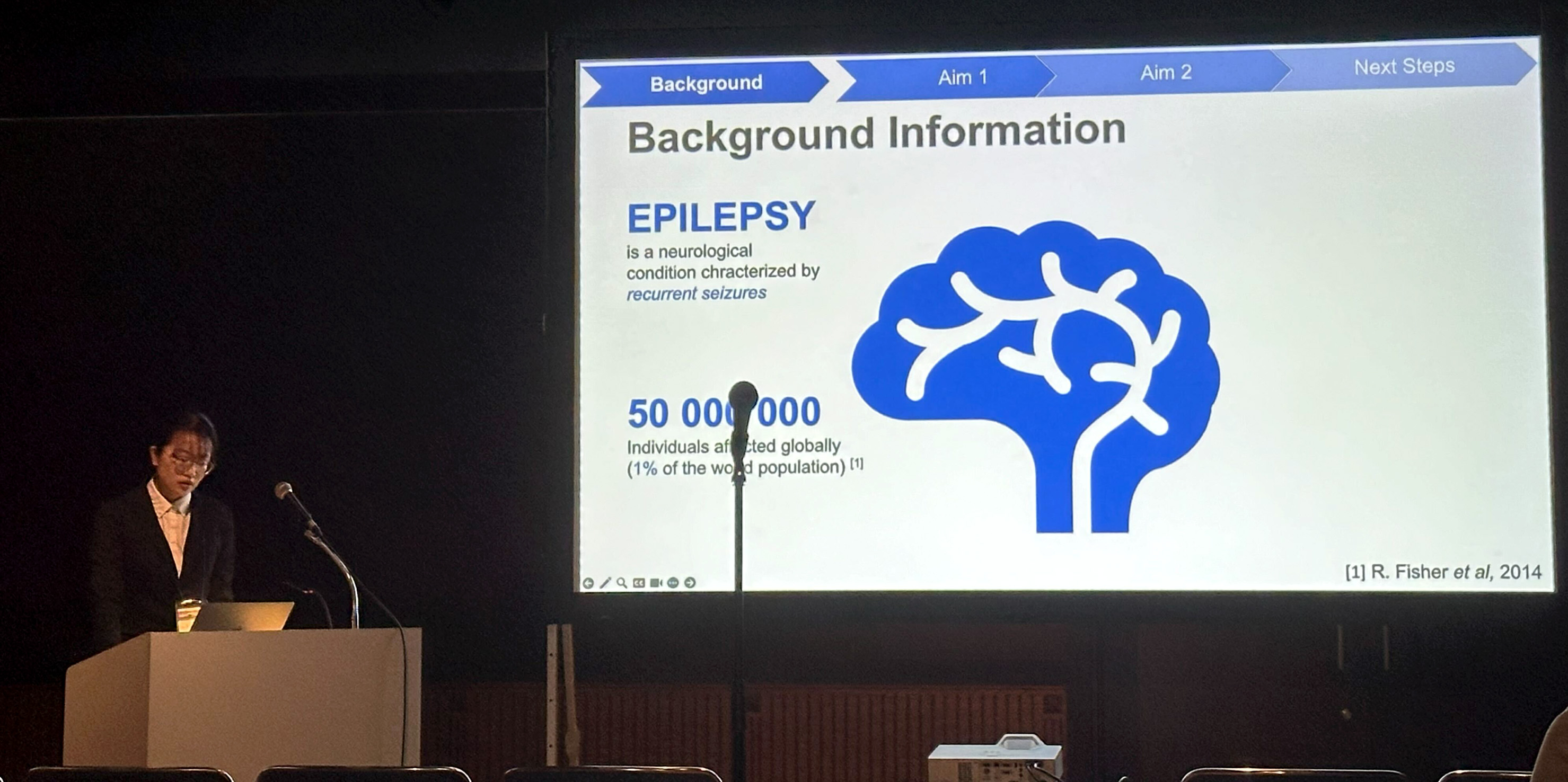
日本で研究発表
原文は英語です



フルブライト・プログラムに応募した時、Johns Hopkins University で分子細胞生物学を専攻する大学生で、てんかん発作について研究していた。自身が高校時代にてんかんと診断されたため、学術的な興味だけでなく、個人的な興味も持っていた。フルブライターとして名古屋大学で取り組んだ研究は、ディープラーニングを用いたてんかん発作の予知だった。
従来の脳波測定ではなく、広く普及しているスマートウォッチなどの電子機器で発作を検知できるよう、心臓超音波信号を用いた研究に重点を置いた。「包括的な目標は、誰でも24時間365日いつでも次の発作を予知できる機器を開発することです。世界で5,000万人いると言われているてんかん患者には、症状にとらわれず、普通に生活を送ってほしいです」
フルブライト・プログラムを知ったきっかけは、日本の高校生を教えるというオンラインサマープログラムに参加し、そこで先輩フルブライターと出会ったことだった。彼に触発され、Johns Hopkins University で4年間にわたって日本語の講義を受けるなど、応募に向けた準備に力を注いだ。このような入念な準備に加え、計算科学という自身のバックグラウンドも活かし、晴れてフルブライターとして、来日した。
名古屋大学の研究室は、フレンドリーで協力的な環境だった。「私が所属した研究室主宰者 (PI) は、研究留学経験が1年あり、英語が流暢でしたので、とても有り難かったです。普段から英語と日本語を交えて話していました。わからないことがあれば、気軽に質問でき、丁寧に説明してくださいました」と振り返る。研究室では、異なるプロジェクトに取り組んでいるメンバー同士であっても支え合っていたので、自然と連帯感が育まれていた。指導教員は、関連分野の日本人研究者たちと交流の場を積極的に設けてくれたという。そうした縁が日米の4つの学会での発表へとつながり、有益なネットワークができた。
名古屋という日本第四の都市での滞在は、留学生活をより実りあるものとした。東京よりも生活コストが低く、交通の便にも恵まれているため、日本中を旅することができた。「名古屋は日本の中心に位置し、どこへ行くにもとても便利で、大好きです」。充実した交通網を利用して、北は北海道から南は鹿児島まで、47都道府県中20もの地域を旅した。
こうした旅は忘れ難い経験となり、ときには思わぬ出会いに恵まれることもあった。元旦の登山で懐中電灯を貸してくれた年上の女性と一緒に歩いたことは、特に印象深い出来事だった。「彼女との交流は今も続いていて、先日も彼女が所属しているバンドの動画を送ってくれました。日本では一度知り合いになると交流が長く続いたり、生涯の友になったり、素晴らしいことだと感じました」
日本へのフルブライト留学は、自身のワークライフバランス観を変えるものでもあった。同僚たちは熱心に仕事に取り組みつつも、趣味にも情熱を注ぎ、上手くそのバランスをとっていたことに感銘を受けた。現在は米国に帰国し、UC San Francisco の医学生として学んでいるが、学んだこのバランスを大事にしている。「授業や仕事がない日には、旅行や登山の機会を通して、自分のコンフォートゾーンから踏み出そうとする友人たちの姿を目の当たりにしました。そういった友人たちの姿は、生涯私の心に刻まれることでしょう」
特にSTEM分野で応募を検討している人へアドバイスする。「応募の際、最初にすべきことは、なぜ日本で研究したいのかを明確にすることです」。自分の留学がどのような相互利益をもたらすかという点が重要だという。さらに、言語の壁を理由に応募を断念して欲しくないと強調する。なぜなら、自身の経験を振り返ると困ったときは指導教員や同僚たちが必ずサポートしてくれたことやフルブライト同期生の日本語レベルは皆違っていたからだと理由を挙げる。「怖がらず自分のコンフォートゾーンから飛び出してみてください。また、フルブライターとして渡日したら、自国を代表して留学しているという自覚を胸に頑張って欲しいです」





